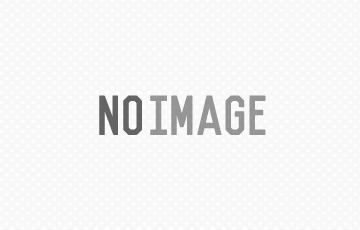――都市伝説と事実の狭間で
筆者には資格取得のために通っていた学校時代の体験がある。その頃、複数回にわたって大型ショッピングモール内にある日本赤十字社の献血ルームを訪れた。明るく清潔な室内、丁寧に対応してくれる看護師たち。初めての献血に緊張していた自分にとって、その空間は思いがけず安心できる場だった。
一方、同じ血液センターの移動採血車(いわゆる「献血バス」)にはどうしても足が向かなかった。地域の大型店舗などの大型駐車場に時折姿を見せる献血バスには、どこか不安を掻き立てられる――という声は、実は珍しいものではない。密閉された車内のイメージ、閉所での医療行為に対する抵抗感が、潜在的な心理的ハードルになっているのかもしれない。
さて、その「献血」の後に届くものとして、多くの人が注目しているのが血液検査の結果通知だ。
一般的に、献血を行うと後日、血液センターから郵送で通知が届く。通知にはコレステロールや中性脂肪、肝機能値など、健康診断さながらの数値が記載されており、ちょっとした「健康の目安」として重宝されている。
しかし、かねてから巷でささやかれる“ある噂”がある。
それは――「献血でエイズ(HIV)に感染していたら教えてくれるらしい」というものだ。
これは本当なのか?
■日本赤十字社の公式見解
結論から述べると、答えは「否」である。
日本赤十字社は明確に以下の方針を掲げている。
「HIVなど感染症の検査を目的とした献血は絶対に行わないでください」
(出典:日本赤十字社 献血に関するQ&A)
実際には、すべての献血血液はHIV抗体やHBs抗原など、感染症に関するスクリーニング検査が行われている。しかし、仮にHIV陽性反応が出たとしても、それは一般的な血液検査結果として通知されることはない。
その理由は二つある。
-
献血は検査の場ではなく、あくまで輸血用血液を確保する医療活動の一環であること
-
感染症に関する結果は、専門医によるカウンセリングを伴わずに郵送通知すべきものではないため、別途対応が必要となること
実際、万一HIVなど重大な感染症の疑いがある場合、日本赤十字社は本人に直接連絡を取る場合もあるが、必ずしもすべてのケースで本人通知を義務付けているわけではない。
また、本人の同意なしにHIV検査結果を外部に知らせることも、個人情報保護の観点から禁じられている。
■「HIV検査をしたいなら、専門の保健所へ」
赤十字も厚生労働省も強調している。
献血は健康診断でもHIV検査でもない。
HIVに関する正確な検査を希望する場合は、各地の保健所や専門外来で無料・匿名で受けられる検査を活用すべきだと強調している。
献血を“ついでの検査”として利用する行為は、最悪の場合、HIV感染者の血液が検査の空白期間をすり抜けて輸血用血液として流通するという、極めて重大なリスクを生む可能性がある。
献血は「善意」と「信頼」に基づく公共の医療行為である。
それを検査目的で利用することは、自分自身の健康管理を誤らせるだけでなく、他者の生命を危険に晒す行為にもなりうる。
■「あの献血ルームの安心感」を守るために
冒頭の体験者が語った、清潔で安心できる献血ルーム。それは、現場の看護師やスタッフの献身だけでなく、献血に訪れる一人ひとりの正しい理解と行動によって支えられている。エイズの不安は、専門の場で、正確に、安心して解決するべきだ。
“あの献血バスの中”も、実は同じくらい信頼できる場所かもしれない――。
だが、その信頼は、私たちの認識と行動にかかっているのだ。

血液センターは、献血者がエイズに感染していた場合、その結果を教えてくれるのだろうか?
厚生労働省が運営している「HIV検査相談マップ」には、次のように書かれている。
「HIV検査の結果は献血者本人には伝えないことになっています。」典拠元 厚生労働省 HIV検査相談研究班「HIV検査・相談マップ」